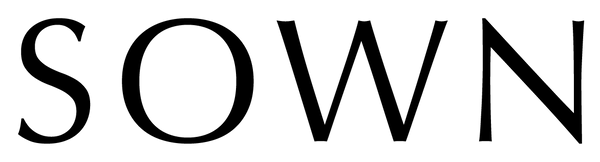朝を整える鍵は「前夜」にある
「1日の始まりは、朝で決まる」──
そんな言葉を聞いたことがあるかもしれません。
たしかに、朝の時間にゆとりがあると、気持ちに余白が生まれます。
けれど、そのゆとりは“前日の夜”に仕込まれていることを、私たちは忘れがちです。
バタバタとした夜、遅くまでの仕事、睡眠不足。
これらが積み重なると、どんなに頑張っても、朝の時間はうまく回りません。
今回は、**「夜から1日を始める」**という視点で、
仕事も、暮らしも、自分自身も整えるヒントをお届けします。
睡眠は、感性のメンテナンス時間
睡眠の大切さは、もう耳にタコができるほど聞いているかもしれません。
でも、つい優先順位を下げてしまうものでもあります。
睡眠は、ただ身体を休ませるだけではありません。
記憶を定着させたり、感情を整理したり、創造性を高める“右脳的な”作用にも深く関係しています。
実際に、睡眠不足の脳は、酔っ払っている状態と変わらないという研究結果もあるほど。
心地よく眠れるかどうかは、次の日の集中力や思考力、ひいては感性の鋭さにも影響してきます。
コンディションが整えば、「短く深く」集中できる
たとえば──
-
コンディション◎の状態で、1時間集中する
-
コンディション△の状態で、3時間集中する
この2つを比べると、前者の方が圧倒的に質の高いアウトプットが生まれます。
20代は気力や体力で突っ走れるかもしれません。
でも30代以降、私たちの暮らしには、仕事以外にも守りたいもの、取り組みたいことが増えてきます。
だからこそ、「整った状態で、短く深く働く」という感覚が、大切になってきます。
コンディションが整っていれば、集中も深まり、本質的な仕事に向き合えるようになるのです。
一石二鳥の働き方:時間の密度を高める
短時間集中の働き方には、2つの大きなメリットがあります。
ひとつは、「仕事ができる人」として信頼されやすくなること。
人間の集中力は約90分が限界だと言われており、それを超えると、どれだけ長く机に向かっていても、効率は落ちていきます。
短く集中→素早く伝達→早いフィードバックという流れをつくることで、
仕事全体のスピードと質が上がり、周囲との信頼関係も強くなっていきます。
ふたつめは、自分の人生に余白ができること。
家庭、趣味、学び、副業──。
働く時間が全てを奪ってしまえば、それらの豊かさはどこにも宿りません。
短時間で成果を出す技術は、仕事を超えて、自分の人生そのものを豊かにする技術でもあるのです。
「夜から逆算する」という時間設計
良い1日をつくるためには、睡眠時間を中心に、1日のスケジュールを“逆算”する視点が必要です。
たとえば、23時に眠ると決めたら、
-
22:30にはベッドに入る
-
22:00には入浴・準備を終える
-
21:00には食事を済ませる
-
19:00には帰宅しておく
-
18:00までに仕事を終える
こうして時間を組み立てることで、自分の時間軸を取り戻すことができます。
もちろん、予定通りにいかない日もあります。
でも、自分のペースを「持っている」ことが、心の安定をつくります。
心地よく眠るための、小さな工夫たち
時間を確保するだけでなく、「眠る質」も意識してみましょう。
-
湯船にしっかり浸かる
-
寝る1時間前にはスマホ・PCから離れる
-
寝室の照明を落とし、音を静かにする
-
読書やジャーナリングなど、脳を“静かに”する習慣をもつ
こうした小さな習慣の積み重ねが、入眠までの導線をなめらかにし、
心地よく眠ることで、感性もゆっくりと“整って”いきます。
おわりに:整えることで、感性が目を覚ます
「夜から1日を始める」──
それは、ただのタイムマネジメントではありません。
睡眠を中心にした暮らしの設計は、
集中力や思考力を高め、感性のゆとりを生み出すことにつながっていきます。
仕事に追われるのではなく、自分の時間を、自分でデザインする。
その最初の一歩は、今日の夜、どんなふうに眠りにつくかから始まるのかもしれません。
それではまた明日──
SOWN 代表
片倉