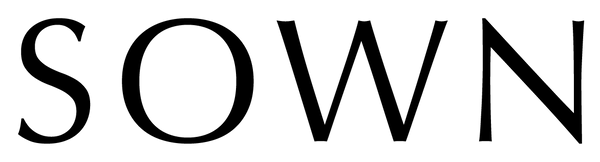はじめに
最近、「花束みたいな恋をした」という映画を観ました。
菅田将暉さん演じる麦くんと、有村架純さん演じる絹ちゃんの恋の物語は、ただのラブストーリーではなく、人生のある時期を切り取った“ドキュメント”のように感じられました。
観終わった後には、胸がぎゅっと締めつけられる切なさと、言葉にできない共感が残り、「あの頃の自分も、きっと同じだった」と静かに振り返るような余韻がありました。
サブカルな共通点──共鳴から始まる恋
二人が出会い、距離を縮めていくきっかけは「サブカル的な共通点」でした。
小説、映画、音楽……。世間的にはマイナーかもしれないけれど、自分にとっては大切なものを誰かと共有できること。その瞬間の喜びは、若い頃ならではの特権のように思えます。
「これ好き?」「わかる!」──そんな会話で一気に心が近づいていく感覚。
私自身も大学時代、同じように好きな作品を誰かと語り合った経験があり、その時の熱量や空気感がフラッシュバックするようでした。
共通の“好き”から生まれる共鳴は、恋の始まりを一層ドラマチックにする。映画はその瞬間を丁寧に描き、観ているこちらまで懐かしい気持ちにさせてくれました。
学生から社会人へ──恋のカタチの変化
物語は、大学生の二人が社会人へと移り変わる過程を描いていきます。
最初は、好きな作品を語り合い、一緒に街を歩くだけで満たされていた二人。けれど社会人になると、仕事や責任がその時間を少しずつ削っていきます。
麦くんは会社員として働き始め、日々の疲れに追われ、本を読む時間が減り、絹ちゃんとの会話も少しずつ薄れていく。
絹ちゃんはそんな麦くんに寂しさを覚え、やがて恋心がしぼんでいく。
「好きなものを好きなだけ語り合えた時間は、もう戻らない」──その切実な実感が、観る者の胸に鋭く突き刺さります。
この変化は、誰もが通る道かもしれません。青春の輝きは、社会に出るとどうしても摩耗していく。それでもなお、人はそこで生きていくのだと突きつけられるのです。
社会人のリアル──喪失と適応
映画の中で、もっとも印象的だったのは、麦くんが自己啓発本を手に取るシーンでした。
かつて小説やサブカルに心酔していた彼が、仕事に適応するために“別の本”を読まざるを得なくなっている姿。
その小さな仕草ひとつに、社会に飲み込まれていく過程の痛々しさが凝縮されています。
さらに胸を打ったのは、「本を読んでも楽しくない。無心でパズドラをやるしかない。」というセリフ。
かつて心を熱くしたものが、もう自分を満たしてくれない。代わりに選んだのは、ただ時間を埋めるためのゲーム。
この虚しさは、多くの人が社会に出てから直面する“現実”そのものではないでしょうか。
好きだったものが好きでいられなくなる瞬間。
その痛みがリアルに描かれていて、思わず自分の姿や周囲の誰かを重ねてしまいました。
もうあの頃には戻れない──喪失の美しさ
ラストのファミレスのシーン。
かつての二人のように、マイナーなバンドの話で盛り上がる学生の隣で、麦くんと絹ちゃんは静かに涙を流します。
「もう、あの頃には戻れない」
その確信は、悲しいけれど、どこか美しくもありました。
人は常に変化し、同じ熱量で語り合える時間は永遠には続かない。
だからこそ、かつての時間はかけがえのない輝きを持ち、二人にとっても、観客にとっても忘れがたい宝物になる。
切なすぎて、私自身も思わず涙してしまいましたが、それと同時に「変わっていくこと自体が人生なのだ」と受け入れざるを得ない感覚がありました。
まとめ──響き続けるもの
「花束みたいな恋をした」は、ただの恋愛映画ではありません。
それは、学生から社会人へと移る過程で失われていくもの、変わっていくもの、そしてもう二度と戻らないものを描いた“人生の断面”でした。
共通の趣味でつながる時間も、社会の中で擦り減る日々も、すべては私たちが生きるリアル。
観終わったあと、「今この瞬間、私が大切にすべき時間は何だろう」と、静かに自分へ問いかけたくなる作品です。
それではまた明日──
SOWN 代表
片倉