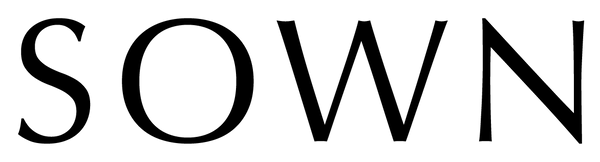「環境が人をつくる」という現実
都会に生まれた子どもたちは、自然と多様な価値観や刺激に囲まれながら育ちます。
通学途中に見かける広告ひとつにも、トレンドや新しい文化の気配があり、週末には展覧会やイベントが身近にある。
そんな「当たり前の日常」が、感性や思考の幅を自然と広げていきます。
一方で、地方に生まれた私たちは、静かで穏やかな時間の中で育つことが多い。
そこには、人との距離の近さや、自然との共存といった“深み”がある反面、情報や機会の少なさから、
「知らないまま過ぎてしまう世界」も確かに存在します。
都会の“豊かさ”と、“見えない疲れ”
東京にはすべてが揃っています。
ファッション、アート、音楽、カフェ、キャリアのチャンス——。
「やろうと思えば、何でもできる」環境は確かに魅力的です。
でもその分、競争も激しく、常に“比較の世界”の中にいる。
気づけば、「もっと上を目指さなきゃ」と自分を追い立ててしまうことも。
豊かさの中にあるのは、同時に“息苦しさ”でもあります。
環境が与えてくれるものは多いけれど、
“どんな心でそこに立つか”によって、その意味はまったく違うものになるのかもしれません。
地方にしか育めない“根”
地方に生まれ育つことは、不利ではなく“土台”を育てること。
自然の中で過ごす時間、人との深い関わり、情報の少なさゆえの“想像力”——。
それは、都会では得がたい「生きる感覚」を育てます。
都会で育った人が“枝”を広げる存在なら、
地方で育った人は“根”を張る力を持っているのかもしれません。
どちらが上とか下とかではなく、世界を支える役割が違うだけ。
どこで生まれるかより、「どう生きるか」
もし、自分が親になったら——
どこで子どもを育てるかよりも、
“どうやって世界の広さを伝えるか”の方が大切だと思うのです。
都会であれば、過剰な情報の中で「取捨選択する力」を。
地方であれば、見えないものを想像する「感受性」を。
どちらの場所にも、育てられる“感性の種”はあります。
生まれた場所がすべてを決めるわけではなく、
その場所をどう感じ取り、どう咲かせるか。
それこそが、生き方のセンスなのかもしれません。
“場所”を超えて、感性を育てる
東京も地方も、それぞれに“光と影”があります。
重要なのは、どちらが優れているかではなく、
どんな経験を通して、自分の感性を耕していけるか。
「世界は広い」と気づいた瞬間から、
人はどこにいても、自由になれるのだと思います。
それではまた明日──
SOWN 代表
片倉