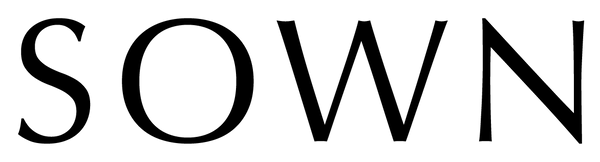どんな仕事でも、新しい提案が求められる場面は必ずあります。
-
新しい商品・サービスの提案
-
新規顧客の開拓
-
次の仕向地の策定
-
社内システムのアップデート
けれど、「新しければ良い」というわけではありません。たとえば突然、まったく新しい提案をしても、相手に受け入れられないことも多々あります。とくに会社やクライアントとの関係性が長ければ長いほど、突飛な提案は警戒されやすいものです。
では、どうすれば「受け入れられる新しさ」をつくれるのでしょうか?
今回は、アートの世界からそのヒントを探ってみたいと思います。
【例1】ジャン=フランソワ・ミレー「種を蒔く人」に見る、“踏襲のうえの挑戦”
ジャン=フランソワ・ミレーの《種を蒔く人》は、今でこそクラシックな作品として知られていますが、発表当時は物議をかもした作品でもありました。
というのも、当時の絵画の主流は、貴族や神話の英雄のような「高貴な存在」が描かれるものであり、農民を正面から描くことは“常識外れ”とされていたのです。
特に、農民のような貧しい人々を称賛するように描くなど、当時の上流階級には受け入れ難いことでした。
しかし、ミレーは「農民の姿」に価値を見出し、大きく足を開き、懸命に種を蒔く姿を象徴的に描きました。
結果、作品は批判と同時に、大きな注目を集めました。
注目したいのは、ミレーが“完全に新しい表現”をしたのではない、という点です。
彼は当時の写実主義という技法を踏襲しながら、「描く対象=モチーフ」だけを変えたのです。
完全に突拍子もない表現ではなく、枠組みの中に新しさを潜ませる──
そのバランス感覚が、作品の力強さを支えていたのです。

-ジャン=フランソワ・ミレー《種を蒔く人》
【例2】ピカソとブラックの“キュビズム”に見る、蓄積の先にある革新
ピカソやブラックが確立した「キュビズム」という表現をご存知でしょうか?
一見すると抽象的すぎて何が描かれているか分からない──
という印象を受ける人も多いかもしれません。
ですが、キュビズムは“突然変異”のように生まれたわけではありません。
そこには長い絵画表現の蓄積と、“段階的な挑戦”がありました。
たとえば、印象派はそれまでの写実主義を打ち破り、風景や人を「印象=光と色のバランス」で表現しました。
さらにゴッホやセザンヌは、点描や遠近法の歪みなど、“目に見えるもの”より“感じたもの”を表現し始めます。
キュビズムは、そうした表現の積み重ねの上に誕生しました。
-
複数の視点から見た対象を、ひとつの画面に収める
-
遠近感や光の方向をあえて崩す
-
対象を幾何学的に再構成する
このように、過去の流れを踏まえながら、“次の一歩”を模索した結果がキュビズムなのです。
だからこそ、最初は理解されなかったとしても、やがて美術の流れとして受け入れられていったのです。
-パブロ・ピカソ《アヴィニョンの娘たち》
「新しさ」とは、積み重ねの先にある
アートの歴史が教えてくれるのは、「まったくのゼロから革新が生まれるわけではない」ということ。
前例や土台を尊重しながら、その一部を少しだけ変える。
その“少しの変化”が、未来を大きく変える可能性を持っているのです。
私たちの仕事にも応用できる、“受け入れられる新しさ”のつくり方
これは私たちの仕事にも共通しています。
たとえば、以下のような場面で考えてみてください:
-
今まで30代のアンダーグラウンドな女性をターゲットにしていたブランドで、突然「次は20代男性向けに!」と提案しても、社内は戸惑うでしょう。
でも、「年齢層だけ変える」「ライフスタイルだけ変える」「打ち出し方だけ変える」──
そうやって“これまでの一部”を残しながら、新しい視点を足していくと、受け入れられやすくなります。
大胆に見えて、実は繊細な配慮に満ちた変化。
それが、本当の意味で“美しい挑戦”なのかもしれません。
まとめ:芸術のように、仕事を組み立ててみる
アートの世界では、時代や風潮を少しずつ踏襲しながら、新しい表現が生み出されてきました。
“受け入れやすい新しさ”とは、積み重ねと挑戦の絶妙なバランスによって生まれるものです。
あなたの仕事の中でも、“すべてを変えようとしない勇気”を持ってみてください。
そして、これまでの文脈に少しだけ風穴を開けるような提案を──
その一歩が、やがて未来のスタンダードになるかもしれません。
それではまた明日──
SOWN 代表
片倉