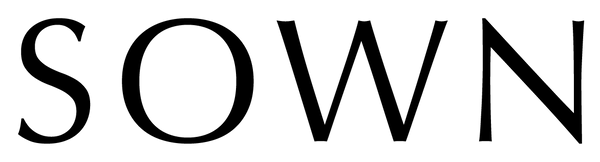はじめに
SNSが当たり前になった今、「承認欲求」という言葉を耳にする機会はとても多くなりました。
どこかマイナスなニュアンスで語られることもありますが、承認欲求そのものは誰もが持つ自然な感情です。
問題は、それをどう表現するか。出し方によって、人との距離を縮めることもあれば、逆に遠ざけてしまうこともあります。
今日は、承認欲求をどう扱うかについて考えてみたいと思います。
学生時代の失敗経験
私自身、学生の頃はTwitterで思ったことを好き放題につぶやいていました。
日常の不満や、イベントに行った時の写真。
そこに「いいね」がつくと、単純に嬉しくて、また次も投稿したくなる。
けれど、ある時ふと「自分は何をやっているんだろう」という気持ちに変わっていきました。
誰かの目を気にして、小さな承認を繰り返し求め続けることが、だんだん虚しくなっていったのです。
あの時の自分は、まさに承認欲求に振り回されていたのだと思います。
直接的な承認欲求
わかりやすい例は、SNSで「いいね」をたくさんもらうこと。
旅行の写真や美味しいご飯の写真をアップし、「かわいい」「かっこいい」と言ってもらいたい気持ち。
これはとても人間らしい欲求ですが、見る側からすれば「またか」と感じてしまうこともあります。
特に、そこまで親しいわけではない人の投稿に対しては、共感や関心が生まれにくいのです。
直接的な承認欲求は、自己開示の一つであると同時に、見る人に「押しつけ」と受け取られるリスクも孕んでいます。
間接的な承認欲求
では、どうすればよいか。
一つの答えは、承認欲求を「表現」に落とし込むことです。
たとえば、音楽を演奏する、絵を描く、文章を書く。そこに自分の想いや経験を込めれば、それは単なる「自己アピール」ではなく、誰かの心に響く作品になります。
この形であれば、あなたの承認欲求は“表現の美しさ”に包まれ、自然と人に受け入れられるのです。
承認を求めるのではなく、結果的に「共感が返ってくる」という順序が理想だと思います。
なかなか難しいこと
ただ、ここで難しいのは、実際に何かを表現している人は、多くの場合「承認欲求のため」にやっていないということです。
純粋に好きだから、楽しいから、表現をしている。その活動そのものが喜びであり、誰かの反応は副産物に過ぎないのです。
だからこそ、欲求の影が見えない発信は心地よく、自然と人を惹きつけます。
承認欲求を満たすために始めた発信も、続けるうちに「好きだからやる」に変わっていければ理想的ですね。
大切な人に満たされよう
不特定多数からの「いいね」は、どれだけ集めても心の奥まで満たされることはありません。
数は増えても、虚しさが残るのはそのためです。
けれども、家族やパートナー、友人といった“本当に大切な人”からの承認は、数に置き換えられない重みを持ちます。
「自分を分かってくれる人が一人でもいる」という実感は、何百の「いいね」よりも深い安心につながります。
結局のところ、承認欲求は量より質なのです。
まとめ
承認欲求は決して悪いものではありません。
それをどう表現するかによって、人との関係を温めることもできれば、形だけの繋がりに消費されることもあります。
大切なのは「承認を求めること」よりも「自分らしく表現すること」。
そして、不特定多数よりも、大切な人との絆に目を向けることです。
承認欲求を恐れるのではなく、うまく表現に変えていくことで、あなたの存在はより豊かに、そして美しく伝わっていくはずです。
今のあなたは、誰に、どんな形で承認されたいと願っていますか?
そして、その気持ちをどのような表現に変えることができるでしょうか。
それではまた明日──
SOWN 代表
片倉