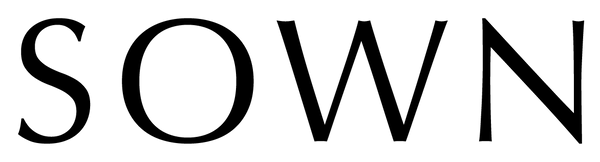はじめに
現在、新橋の「アドミュージアム東京」で開催されている「わたしたちはわかりあえないからこそ展」に行ってきました。
タイトルからして少し挑戦的で、男女やジェンダーの問題に切り込む展示。
実際に見てみると、普段何気なく過ごしている社会の中に、いかに“無意識の偏り”があるかを改めて考えさせられる内容でした。
今日は、その感想をいくつかのテーマに分けて書いてみたいと思います。
男女のジェンダー
展示では、男女の違いを単純に「男/女」というラベルで語ることの難しさが描かれていました。
「男性はこうあるべき」「女性はこう振る舞うべき」といった固定観念が、いかに社会に根強く残っているか。
例えば職業のイメージ、日常会話での役割、家庭での立場…。
どれも「誰が決めたの?」と問い返したくなるような無意識のルールが存在しているのです。
広告に女性を起用する
特に印象的だったのは、広告における女性の扱いです。
「美しさ」や「可愛さ」を強調される女性像は数え切れないほどあり、商品そのもの以上に「女性らしさ」が消費されてきた歴史があることを実感しました。
一方で、最近は「強さ」や「自立した女性」を描く広告も増えてきていますが、それもまた“男性的な強さ”の基準に合わせているのではないか?という問いかけもありました。
広告は社会を映す鏡。
だからこそ、その変化を追うことは時代の価値観を知る手がかりになるのだと感じました。
学業やスポーツでの男尊女卑
展示の中には、学業やスポーツでの男女格差を示すデータもありました。
「女の子は理系が苦手」「男の子は体力がある」という刷り込み。
これがどれほど進路や自信に影響してきたかを数字で突きつけられると、笑い話では済まされないと痛感します。
特にスポーツの場では、ルールや環境そのものが男性基準で設計されてきた部分も多く、「努力以前にスタートラインが違う」という現実を突きつけられました。

妊娠、出産という女性だけの要素
さらに考えさせられたのが、妊娠・出産に関する展示でした。
これは生物学的に女性にしか担えない要素ですが、それを社会全体で支える仕組みがどれだけ整っているかというと、まだまだ十分ではありません。
キャリアを積みたいと思っても「出産するなら…」と暗黙の圧力を受けることもある。逆に、子どもを持たない選択をすると「女性なのに」と言われることもある。
こうした現実を前に、「わかりあえないからこそ」理解し合おうとする努力が必要なのだと感じました。
まとめ
「わたしたちはわかりあえないからこそ展」というタイトルの通り、男女の違いはゼロにはできません。完全にわかり合うことも難しい。
でも、だからこそ「相手の立場を想像してみる」「その人の現実を知ろうとする」ことが大事なのだと思います。
展示を見て感じたのは、「わかりあえない」という距離感が前提にあるからこそ、歩み寄ることができる、というメッセージでした。
それではまた明日──
SOWN 代表
片倉