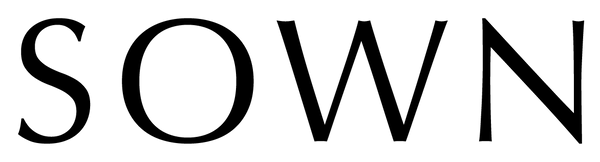・はじめに
一日の終わり、布団に入って明かりを消すと、なぜか頭の中が活発になり、いろいろなことを考えてしまう。
明日の予定から過去の後悔まで、普段なら気にも留めないことが次々と浮かんできて、眠れなくなる──
そんな経験は多くの人にあるのではないでしょうか。
今日は「夜に考えごとをしてしまう理由」と「そこからどう付き合っていけばいいのか」を考えてみたいと思います。
・脳の仕組み
夜になると、副交感神経が優位になり、体はリラックスモードに入ります。
しかし脳は、昼間の情報を整理する時間に入り、記憶の定着や感情の処理を進めます。
そのプロセスの中で、忘れていたことや気になる出来事が浮かび上がってくるのです。
つまり「夜に考えごとをしてしまう」のは、脳がしっかり働いている証拠でもあります。
・静けさがもたらす作用
夜は、外界からの刺激がぐっと減る時間帯です。
スマホを閉じ、街の音も静まり返ると、自分の心の声がより鮮明に聞こえてきます。
昼間は周囲の騒音にかき消されていた不安や希望が、夜になると前面に出てくるのです。
ある意味で夜は、心と深く向き合うための「感性の時間」とも言えるでしょう。
・ジャーナリングという習慣
そんな夜の反芻思考におすすめなのが「ジャーナリング」です。
ジャーナリングとは、頭に浮かんだことを紙に書き出す習慣のこと。
内容はまとまっていなくても、文章になっていなくても構いません。
「明日のプレゼンが不安」「あの時の会話が気になる」など、思いつくままに書き出してみるだけで、脳の中で堂々巡りしていた思考が外に出ていきます。
私自身も、夜なかなか眠れないときにジャーナリングを試したことがありますが、頭の中が整理されて「あ、もう考えなくてもいいや」と思える瞬間がありました。
不安を「頭の中だけ」で抱えるのではなく、「紙に預ける」だけで、驚くほど気持ちが軽くなるのです。
・ポジティブな夜の思考
夜の考えごとには、ネガティブな側面だけでなく、ポジティブな面もあります。
たとえば、ふと浮かんだアイデアをメモすることで、翌日につながる創造の種になることもあります。
偉大な作曲家や発明家が夜中にインスピレーションを得た、というエピソードは数多くあります。
夜は不安と同時に、創造性を引き出す特別な時間でもあるのです。
・上手な付き合い方
大切なのは、夜の思考に「振り回されないこと」。
ジャーナリングのように書き出す習慣を取り入れたり、軽いストレッチや瞑想をすることで、頭と心を整理しやすくなります。
夜の考えごとを“敵”とするのではなく、心と対話する時間として受け入れられれば、それはむしろ人生を豊かにする時間になるはずです。
・まとめ
夜に考えごとをしてしまうのは、人間らしい自然な働きです。
静けさの中で、脳と心がようやく自分自身に向き合うからこそ、思考が活発になるのです。
大事なのは、それをどう扱うか。
ジャーナリングで外に出す、アイデアとして受け止める──そうした工夫をすることで、夜の思考は不安の種ではなく、感性や創造性を深める特別な時間に変わっていくのではないでしょうか。
それではまた明日──
SOWN 代表
片倉